Microsoftやグーグルも採用するメール効率化法『インボックス・ゼロ』
- 伊賀上真左彦

- 2024年12月18日
- 読了時間: 7分
更新日:2024年12月19日

現代のビジネス環境では、毎日大量のメールが届き、その管理に多くの時間を費やしています。ビジネス先進国の欧米では、社会人平均で毎日6時間弱をメールに費やしているとされ、まさにビジネスの大半の時間をメールに費やしています。その効率化はビジネスの効率化にとって、最も重要なものと言ってもよいでしょう。
そんな中、MicrosoftやGoogleなどの大手企業が採用している効率的なメール管理法が『インボックス・ゼロ』です。この方法は、受信トレイを常に空(ゼロ)の状態に保つことを目指し、生産性を向上させるためのアプローチです。Googleは社員3万人に研修を受けさせていますし、Microsoftは機能としてOutlookに取り込んでいます。インボックス・ゼロの考え方を知ることで、gmailやOutlookをより簡単に、ミスなく使うことが出来ます。
インボックス・ゼロとは?
インボックス・ゼロは、メールの受信トレイを効率的に管理し、未処理のメールをゼロに保つことを目指す手法です。この概念は、メール管理の専門家であるマーリン・マンによって提唱されました。インボックス・ゼロの目的は、単にメールをゼロにすることではなく、メールとの付き合い方を見直し、生産性を向上させることにあります.
メールに対して行う4つの処理
インボックス・ゼロの基本は、メールを「削除する(Delete)」「実行する(Do)」「保留する(Defer)」「転送する(Delegate)」の4つのルールを使い整理します。これを4Dメソッドと呼びます。
削除する(Delete): 対応する必要があるか判断します。ない場合はします
実行する(Do): 2分以内で返信できる場合、すぐに返信します
保留する(Defer):すぐに対応できない場合、保留フォルダーに移動させます
転送する(Delegate):他に適した担当者がいる場合、その方にメールを転送します
インボックス・ゼロはメールの処理をシンプルにして、効率的に、精神的な負荷を減らして管理する方法です。メールに対して4Dメソッド以外の処理を行う事はありません。
メールは数時間に1回、まとめて読む
通知をオンにして、常時メールをチェックする、ということはインボックス・ゼロでは推奨されていません。これはメールを処理する時間と、メール以外の仕事を処理する時間を分離し、それぞれ集中するためです。類似した仕事をまとめて行う効率化法をタスク・バッチングと呼びます。インボックス・ゼロもこの考え方を用いています。
メールの常時チェックを続けることは精神的な負荷が高いですし、集中力を低下させ、メール以外の仕事の効率を落としてしまうためです。人間は一度集中力が落ちると、回復に23分かかることが研究で分かっています。メールを読む行為は集中力の低下を招きます。
フォルダー分けは使わない
インボックス・ゼロではフォルダー分けによるメールの管理は行いません。使うのは受信トレイと、アーカイブの2つだけです。
メールを数十、もしくは数百のフォルダーに入れて管理している人も多いですが、フォルダー分けしたメールを、後日再度読む割合はどの程度でしょう?1%もないのではないでしょうか?その場合。メールを整理するのに要する時間の99%は無駄、ということになります。こういった無駄な作業を減らすことで効率化しますし、精神的な負荷を減らすことにもつながります。
重要度に応じたメールの処理をしない
インボックス・ゼロでは重要度に応じたメールの処理を行いません。それにより作業を効率化しています。よく「このメールは2時間後に返信するのがベスト」といった判断を行い、メールの重要度や個別の状況に応じて、返信する時間を調整する人がいます。2時間後に返信する場合、2時間の間そのメールのことを頭の片隅に置いておく必要がありますし、そのまま返信を忘れるリスクもあります。そういった無意味な保留をせず、処理できるメールはその都度処理し、削除することで忘れるようにします。
受信簿をタスク・リストとして使う
インボックス・ゼロでは処理が終わったメールをすぐに削除します。そのため、受信トレイに残っているメール=未処理のメール=タスク・リストとして機能します。受信トレイの中にあるメールを極力少なくすることで自分が抱えるタスクを減らし、精神的な負荷を低減します。
メール以外のタスクに関しては、自分宛てにメールをして、他のメールと一緒に管理するとよいでしょう。例えば口頭で仕事を依頼された場合、内容を自分宛てにメールします。タスクを紙の手帳、付箋など複数の形態で保存している人がいますが、管理の負荷が増えます。極力メールのみに一元化し、受信トレイで管理します。
インボックス・ゼロのメリット
①ストレスの軽減
受信トレイが常に整理されていることで、未読メールが山積みになるストレスから解放されます。
②効率的な作業
必要なメールをすぐに見つけられるため、業務効率が向上します。
③集中力の向上
メール管理に時間を取られることが減り、他の重要な業務に集中できるようになります。
インボックスゼロへのスムーズな切り替えを行う2つの方法
メール管理の効率を上げ、精神的な負荷を減らす効果も持ったインボックスゼロですが、従来のフォルダー分けの管理とは違いが大きく、焦って切り替えるとメール見逃しや二重対応などの事故が発生する可能性があります。半年程度かけて、徐々に切り替えることをお勧め
①重要度が低いフォルダーは使用を止める
後から見直す可能性が低いメールが入っているフォルダーは使用をやめ、受信トレイとアーカイブで管理するようにしましょう。
②メールの厳密な管理が必要なフォルダーは共有メールボックス、もしくはグループメールボックスで管理
後から見直す可能性が高いメール、および将来に他の人に引継ぐ可能性が高いメールが入ったフォルダーは、グループメールアドレスなど専用のメールアドレスを作り、そちらにメールを保存しましょう。他の人に業務を引き継ぐ場合も、グループメールアドレスへのアクセス権を設定するだけで完了します。上司にもアクセス権を設定すれば進捗の確認が可能となり、報告の負荷も減ります。
実際の運用
以上がインボックス・ゼロの基本的な方法となりますが、使っているメールアプリの種類や、皆様の仕事内容によって若干のアレンジを加えた方が良い場合もあります。以下、参考に私が行っている方法をご紹介します。
①受信トレイ以外に「広告」「重要」の2つのフォルダーを作る
「広告」フォルダーは、情報収集のために登録したメール・マガジンなどを自動仕分けの機能を使って送っています。時間がある時にしかこのフォルダーはチェックしません。また読み終わってもアーカイブに送ることはせず、そのまま「広告」フォルダーに入れたままとしています。
「重要」フォルダーは後日再び読む可能性があるメールを入れています。例えば訪問予定がある得意先の住所、入場券のPDFやQRコードが含まれたメールなどです。外出時にスマホの小さい画面でメールを探すのは難しい作業です。ですので外出前に必要なメールをここに移動しておきます。
②「保留」フォルダーを作らない
すぐに対応することが難しいメールは通常、保留フォルダーに入れますが、私は受信トレイに置いたままとし、アウトルックの分類項目の機能で保留に分類します。以前は「保留」フォルダーを用いていましたが、私の場合は100件を超えるメールがあふれ、管理が困難となりました。そうならないよう受信トレイに置いたままとし、目が届きやすいようにしています。
まとめ
インボックス・ゼロは、シンプルでありながら効果的なメール管理術です。この方法を実践することで、受信トレイを常に整理された状態に保ち、メール対応のストレスを減らし、業務効率を向上させることができます。インボックス・ゼロはGTD(Getting Things Done)というタスク管理手法をメールに適用したものとされています。ご興味がある人はGTDも調べてみると良いでしょう。
インボックス・ゼロもディープ・ワークもですが、海外の業務効率化手法の多くは、人間のストレスを減らし、手順を簡略化することで効率化を目指しています。精神論、根性論を振りかざす場合が多い日本での業務効率化とはこの点が大きく異なります。日本式効率化法と海外式効率化法、どちらがより効率的でしょう?結果を見れば明らかですね。
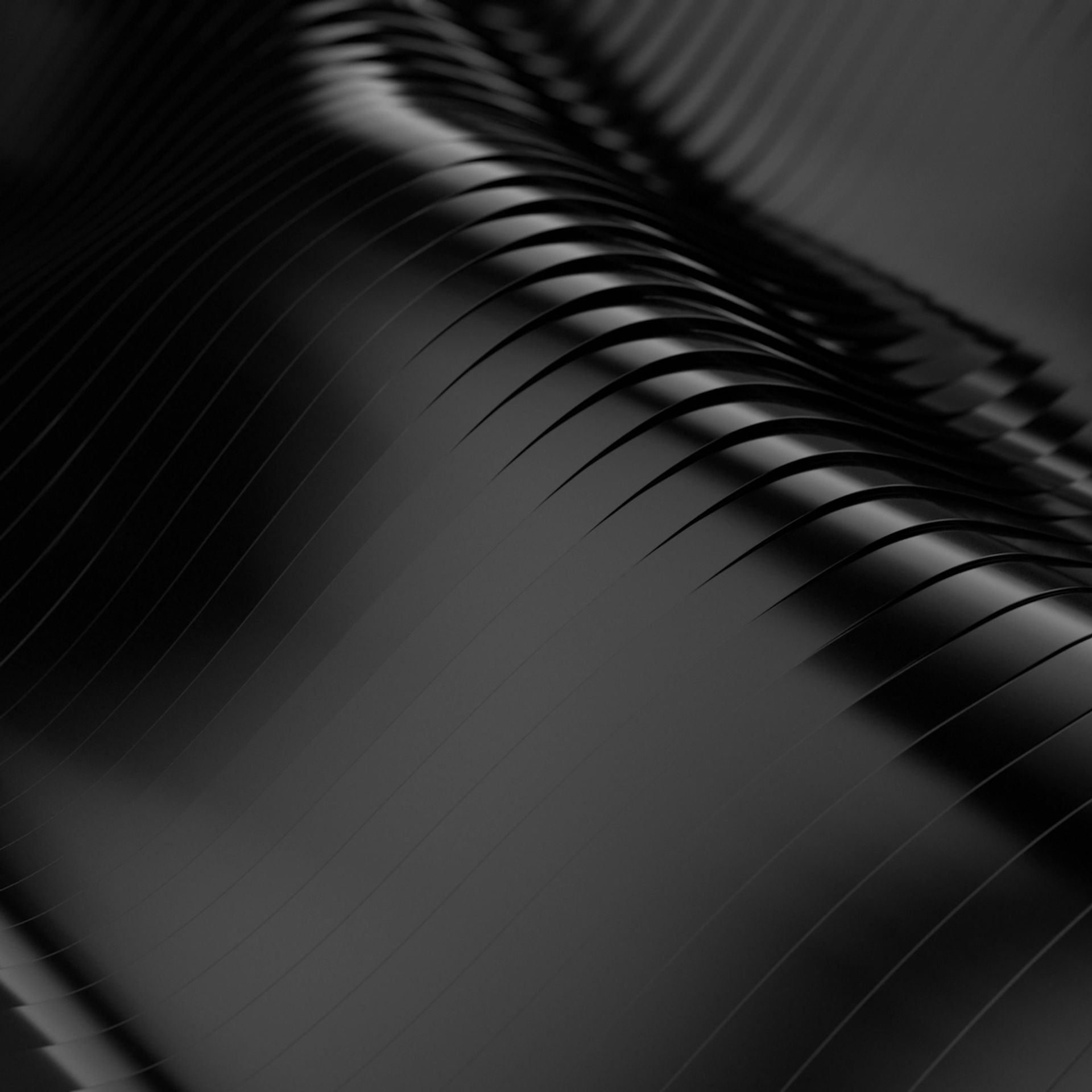



Comments